最初にもらう資料が、プロジェクトの成否を決める
「屋根に太陽光発電を載せたいので、まず見積もりをお願いできますか?」
これは、よくあるお客様からのご相談の入り口です。
しかし、ここで焦って見積もりだけ出してしまうと、後々トラブルや無駄な手戻りが発生するリスクがあります。なぜなら、太陽光発電システムの試算・設計・施工は、建物・契約・環境などの多面的な情報をもとに成り立つものだからです。
実際、初期段階で「最低限押さえておくべき資料」がそろっていないと、
- パネルが思ったより載らなかった
- 売電できないことが後から判明した
- 想定より電気が使えず、経済効果が薄い
など、導入判断に大きな影響を及ぼす失敗が起こりえます。

そこでこの記事では、建物屋根に太陽光発電システムを設置する際、検討初期に必ず揃えておきたい資料リストを、わかりやすく解説します。
初動で必要な資料一覧(屋根設置型 太陽光発電編)

建物関連資料|設置可否と構造の基本を押さえる
| 資料名 | 内容・目的 |
|---|---|
| ★建物の設計図(平面図・立面図・屋根伏図) | 屋根の形状・寸法・勾配を確認。パネルレイアウトや荷重計算に必要。 |
| 建築確認申請書・検査済証 | 建物が法的に問題なく建てられているかを確認。増築・改築履歴もチェック。 |
| ★建物構造の概要(鉄骨・木造・RCなど) | 荷重・施工方法の選定に必須。 |
| ★屋根材の種類(折板、瓦棒、スレートなど) | 架台・施工方法の選定に直結する重要な情報。 |
旧耐震基準の建物の場合は注意
建築基準法は1981年6月1日に改正されており、設計の際に用いる基準値も改正後の数値です。
太陽光を検討されている建物が、1981年6月1日より以前の旧耐震基準で建築されている場合、屋根への太陽光発電システム設置は推奨されていないため、特に注意が必要です。
建築確認は原則不要!?
国土交通省は、屋根に設置する太陽光発電設備(屋内的用途がない・人が立ち入らないもの)については、建築確認申請が原則不要であると判断しています。
- 太陽光パネル設置のための架台下に、メンテナンス以外では人が立ち入らないこと
- 架台下の空間が居住・作業・集会・物品の保管など、「屋内的用途」に供されないこと
ですが、、、建築確認不要といっても、建築基準法の構造耐力基準や防火基準への適合が求められる点は変わりません。特に、旧耐震基準の建物では構造安全性の確認が重要である点には十分な配慮が必要です
ポイント!
・太陽光販売業者とのご商談の際は、最低限★印の資料を用意しましょう。
・特に古い建物の場合には、耐震診断書をされるなど、設置荷重に対する安全確認が必要です。
土地・権利関連資料|所有者・契約者・設置権限を明確に
| 資料名 | 内容・目的 |
|---|---|
| 登記簿謄本(全部事項証明書) | 建物の所有者と申込者の一致を確認。契約書の主体にも関わる重要項目。 |
| 賃貸借契約書(借地・借家の場合) | オーナーの設置同意の有無や、使用権の範囲を明確に。 |
| 建築協定・地区計画など | 一部地域で屋根上の工作物に制限がある場合があるため、要チェック。 |
土地の所有者は他人、建物は自社、これって大丈夫なの?
土地の所有者の承諾なしに太陽光を設置すると…、 法的に重大なリスクが発生します!
たとえ建物が自社所有であっても、その建物が他人の土地に建っている場合(借地・地上権など)、屋根の上に太陽光パネルなどを設置する行為は、土地の使用権限を逸脱する可能性があります。
屋根が自社の所有であっても、屋根がのっている土地の所有者が他人である以上、その土地を使った工作物の設置には“地主の承諾”が必須です。
ポイント!
・借地の上に自社の所有の建物の場合は注意が必要です。太陽販売業者が時間をかけた結果、このような事由が発生してしまうと、余計なトラブルを招く可能性がありますので、商談の際にはお伝えしましょう。
電気関連資料|電気の使い方が経済性を左右する
| 資料名 | 内容・目的 |
|---|---|
| ★受電契約内容(契約電力・種別など) | 高圧/低圧の判断に必須。連系方式やインフラ工事要否を判断。 |
| キュービクル図面(高圧受電の場合) | 太陽光接続可能な場所や容量を検討。 |
| ★電気料金明細(直近12ヶ月分) | 自家消費量・削減効果の試算に。消費傾向を把握できる。 |
| ★30分単位のデマンドデータ | 時間帯ごとの消費ピークを把握し、蓄電池やピークカット戦略に必須。自家消費率の試算にも活用。 |
ポイント!
・太陽光販売業者とのご商談の際は、最低限★印の資料を用意しましょう。
・最適な削減効果を試算するためには、非常に重要な資料になります。
30分デマンドデータが必要な理由
30分ごとの電力使用量(kW)を記録したデータで、特に高圧受電契約の事業者で重要です。
| 活用内容 | 説明 |
|---|---|
| ピーク電力の把握 | 太陽光が発電しない時間帯の負荷や最大需要を明確に。 |
| 蓄電池容量設計 | 夜間電力のカバーやピークシフト設計の根拠になる。 |
| 自家消費率の計算 | 売電よりも自家消費を優先した設計に必要不可欠。 |
| ※現在、購入している電力会社にお問い合わせしてください。 | |
屋根・建物の現況に関する資料|安全な施工のために
| 資料名 | 内容・目的 |
|---|---|
| 屋根の修繕履歴(防水工事など) | 経年劣化や再塗装の有無を把握。設置前の補修判断に必要。 |
| 点検記録(雨漏り・ひび割れなど) | 施工後のトラブル回避。設置の是非判断にも。 |
| 写真(屋根上、分電盤、周辺建物など) | 影の影響や配線経路の確認。 ドローン写真があればさらに正確。 |
| 設備図面(空調、換気口、避雷針など) | パネル配置や架台設計時の干渉回避に役立つ。 |
ポイント!
建物の状態をご商談の際に伝えられる事が、設置後も心配なく太陽光発電設備をご使用できます。
防水工事や遮熱塗料を施している屋根での注意点
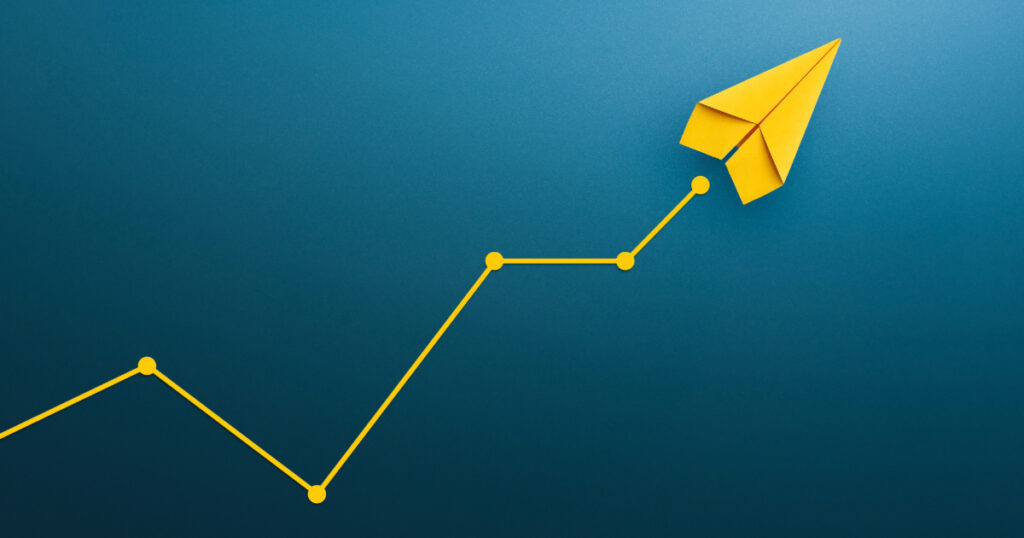
施工前に確認していないと、設置後に雨漏りが発生しても誰も責任を取れない状態になります。
防水層の破損リスクを避けることが最重要
太陽光パネルを取り付ける際、多くの場合「架台を屋根に固定する」必要があります。その際にビスやボルトで屋根材に穴を開けることがありますが、この穴あけ行為が防水層を破壊する危険性があります。
防水工事や遮熱塗装は、施工後10年~15年の保証がついていますが、太陽光パネルを設置することで防水保証等が消失するの可能性もあります。そもそも太陽光と防水工事・遮熱塗装は目的が異なるからです。
具体的なリスク:
- 雨漏りの原因になる
- 既存の防水保証が無効になる可能性がある
防水は、あくまでも建物の資産維持のためです。 - メーカー保証・施工保証の対象外になる可能性もある
〈対策〉
・穴開け不要の支持金具・接着架台・バラスト式(重り固定)などの施工方法を検討する。
・既存の防水施工会社に「穴開けの可否・再補修の範囲・保証の継続条件」を確認する。
・古い屋根ほど「設置前に防水処理」が検討が必要です。
遮熱塗料の効果を損なわない施工計画
遮熱塗料(白色や反射性の高い塗装)を施した屋根に太陽光パネルを敷設する場合、以下のような点に注意が必要です。
注意点:
- パネルで遮熱塗料の表面が隠れてしまう部分は、もはや“反射”できず、部分的に熱がこもる可能性がある
- 一部の遮熱塗料は非常にデリケートで、施工時の足跡や機材の擦れでも性能が劣化することがある
〈対策〉
・遮熱塗料を塗った後、一定期間経ってから施工する(塗料が完全硬化した後)
・必要に応じて、パネル設置エリア以外だけに遮熱塗装を施すなどの対応も有効です。
ポイント!
ソーラーパネルは、副次的効果ではありますが、屋根面に直接日射が当たるのを防ぐ“日傘”のような働きをするため、屋根の表面温度を下げ、屋内への熱の侵入を軽減する効果が認められています。
設計・構造上の制約にも注意
- 防水層や塗膜の厚みや材質によっては、ビスやアンカーの食い込みが不十分になる場合があります
- 屋根が金属系で遮熱塗料が吹付けられていると、高温変形しやすくなり、熱膨張に弱いケースもあります
〈対策〉
・架台の施工仕様書にある固定方式が、防水層と合っているかを事前にチェック
・必要に応じて、構造設計者による評価・確認を依頼された方が無難でしょう。
ポイント!
・設置後に不具合が発覚しても、保証の対象外になる可能性があるため要注意ですので、経験のあるEPC事業者を選定しましょう。
まとめ:資料が揃えば、太陽光発電は“成功するプロジェクト”になる

太陽光発電の設置は、単なる「パネルを載せる工事」ではありません。電力、建築、法務、構造、安全、コストといった複数領域にまたがる総合的なエネルギー投資になります。

その成功を左右するのが、今回ご紹介した「初動でそろえるべき資料」です。
これらの資料が揃っていれば:
- 正確な発電量・自家消費量の試算が可能
- 設計・施工の精度とスピードが大幅アップ
- 余計な工事・コストを未然に防げる
- 補助金・申請書類の不備が減る
- 契約後のトラブルが起きにくい
つまり、資料の充実=プロジェクト成功率の高さ、です。
「何から始めたらいいか分からない」という方は、ぜひ、当社までご連絡ください。経験豊富なパートナー連携をしながら取り組むことが可能です。
「初動」が整えば、「結果」も変わります。
太陽光導入を成功に導く第一歩として、資料の準備が非常に重要です。






















